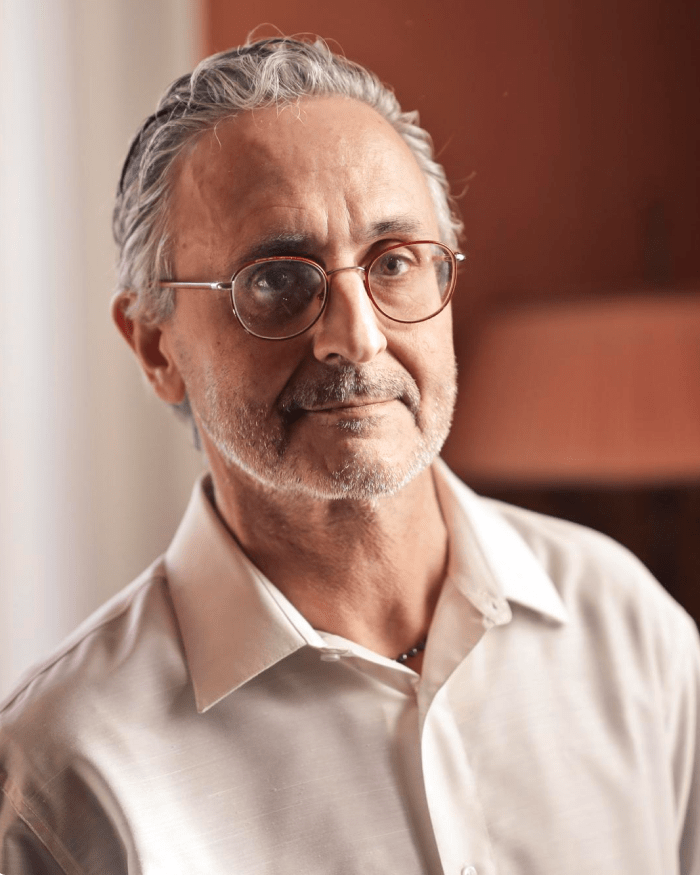英国に拠点を置く暗号カジノレビューと暗号カジノゲームに関する情報サイト – CryptoCasinos360は、非公開の金額でRingo Sancoとそのすべての関連資産を取得したことを発表しました。
CryptoCasinos360は8月上旬にRingo Sancoを買収し、日本のブランドを成長するCryptoCasinos360ブランドに統合する計画を持っています。2022年末までに、リンゴ・サンコはCryptoCasinos360の連結売上高の主要な部分を占めることになります。
リンゴ・サンコは、携帯電話およびその関連機器に特化した日本の情報サイトとして成長しています。長年にわたり、携帯電話に関する有益な情報を読者に提供し、ユーザーの信頼を獲得してきました。
Ringo Sancoには、毎日アプリ関連のトピックを扱う、プロフェッショナルで経験豊富なアナリストチームがあります。したがって、このチームはCryptoCasinos360がモバイル暗号通貨ギャンブルのレビュー、トップリスト、さまざまなガイドを改善するのを助けることができるようになります。
CryptoCasinos360について少し
CryptoCasinos360は、トップ暗号カジノと暗号カジノゲームに関する信頼性の高い情報を提供する情報サイトです。新進の暗号カジノアフィリエイトブランドは、デジタル通貨をオンラインで賭ける際のプレーヤーの安全性を高めることを目指し、イーサリアム、ビットコイン、その他のコインを使用する数多くのカジノウェブサイトを分析しました。ユーザーは暗号ギャンブルのための安全なサイトの健全な選択にアクセスすることができます。
この成長中の暗号カジノアフィリエイトブランドは、英国のマンチェスターに本社を置き、2016年に始まりました。アクセス可能な、機敏で純粋に創造的なカジノ専門家の小さなグループのみを備えているにもかかわらず、彼らのレビュアーは長年にわたって経験を増やし、それが彼らの成長を助けてきました。
CryptoCasinos360は、プレイヤーがGameStopで登録しても、デジタル通貨を受け入れるサイトから最高のギャンブル体験を見つけることができるようにすることを目指しています。このサイトのレビュー専門家は、ライセンス、安全性、ボーナス、その他の機能をチェックしながら、暗号ゲームとそのアクセス方法について詳しく知ることに努めています。
暗号ギャンブルアフィリエイト市場のリーディングブランドへ
CryptoCasinos360のRingo Sanco買収の動きは、市場で長年の経験を持つより専門的なモバイル暗号ギャンブルのレビュアーをもたらすので、非常に有益な投資です。現在、CryptoCasinos360は、そのパートナーのゲーム会社やオンラインスポーツブックに10倍以上のトラフィックを送ることができます。
Ringo Sancoと手を組む前、CryptoCasinos360は暗号カジノのアフィリエイト分野で重要な役割を担ってきました。この買収により、CryptoCasinos360は、カジノアフィリエイト業界の新しいセグメントを征服するという夢に近づきました。また、競合他社が市場で提供したものとは異なる魅力的なポートフォリオをその信奉者に提供します。
CryptoCasinos360の究極の目標は、英国および海外で認知されたオンライン暗号ギャンブル市場の主要ブランドになることです。Ringo Sancoは、CryptoCasinos360が暗号ギャンブルアプリのセクションを拡大し、プレーヤーのためにますます多くの貴重な情報をもたらすことを可能にする、認識されたブランドです。